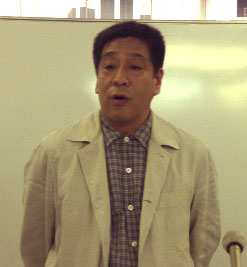
「日本芸能再発見の会」第36回例会(2002年6月15日)は、漫才作家の加納健男さんに「漫才作家及び漫才の台本の生活と意見」と題してお話をうかがった。
漫才には「つかみ」がありますから「つかみ」の話から、と加納さんは始められた。漫才作家でも、「つかみ」を書く人と書かない人がいるが、昔の漫才は妙な「つかみ」がかなりあった。「ちょっと聞いたんやけど、あんたアホやそうやな」ではじめたり、「ステテコのすそにキリギリス飼うてんのやてな」「何言うてんねん、コオロギや」という「つかみ」。さらにはハゲ頭に手をかざしてぬくもるというのもあったとか。自己紹介型は漫画トリオから始まり、定番となったのはレツゴー三匹あたり。音楽ショウの場合はテーマソングが必ずあった。漫才師から「つかみネタは書かんでええで」と言われながらも書くのが好きな作家さんもいたそうである。
加納さんは大阪万博終了後、ABCラジオ「みんなの歌謡曲」の「あなたも漫才作家」というコーナーに投稿し、ダイマル・ラケットにほめられ、漫才作家を志した。当時、神戸新聞の夕刊に広告が乗っていた漫才作家協会編「漫才系図」を購入したところ、手紙に「漫才作家を養成する協会です。例会に来ませんか」と書かれており、入ることにした。この漫才作家協会は、漫才作家くらぶから秋田實さんと藤井康民さんが松竹芸能を脱退したために分裂してできたもので、丹田重雄さんが中心となっていたものである。そして、漫才作家協会は松竹芸能の文芸課につながっており、ここで書いた台本は松竹芸能に売り込むことになっていた。
加納さんは月二回、松竹芸能文芸課へ台本を持ち込み、「本読み」をし、審査に通ったものが採用され、台本料が支払われた。しかし、最初は審査を通っても芸人さんはなかなか舞台にはかけてくれなかったそうだ。ちなみに最初に審査を通った台本は、上方柳次・柳太のために書いた「原因不明」というもの。二十分オーダーで原稿用紙にして二十枚程度だったそうである。初めて演じてもらえた台本は麻理奈々・美々(奈々は中田ダイマルの娘)の「恋人の車」。審査に通ったら六千円のギャラをもらえた。
昭和四七年ごろ、NHKの「演芸台本研究会」に誘われ、そこで「上方演芸会」向けの台本を書くようになった。当時は松竹芸能に非常勤嘱託で所属していたが、NHKのおかげで他社の漫才師の台本も書くことができ、それが勉強にもなった。
非常勤から常勤に、そして正社員となったが、昭和五一年にフリーとなった。フリーになると、月に十本は書かないと生活していけなかった。実際は、ABCの「笑ってゴーゴー」などの構成をしたりと放送作家の仕事が入り、台本を書けないというジレンマもあったそうである。
台本を一番多く書いた漫才には、松竹芸能ではちゃっきり娘、ジョーサンズ、若井ぼん・はやと、吾妻ひな子、吉本興業では人生幸朗・生恵幸子、若井小づえ・みどりなどであったそうである。
台本を意識させないのが漫才作家の喜びであり、寂しさでもあると、加納さんは言う。最初に「漫才作者」を名乗ったのは秋田實で、横山エンタツ・花菱アチャコがしゃべくり漫才を作り上げた時に台本が必要となったのである。それまでの「万歳」は音曲、踊り、仕草、しゃべりの四つのパターンに分類される(前田勇による)祝いの芸であり芸の素養が必要であったが、しゃべくり漫才はしゃべりそのものが芸になるいわば「無芸」の芸となった。ここにエンタツ・アチャコの革新性がある。それまでの「万歳」は諸芸の吹き溜まり、「擬(もどき)」であった。音頭、軽口、俄が含まれていた。エンタツ・アチャコの時に吉本興業の橋本鐵彦が「漫才」と命名(昭和七年ごろ)した。これは全てのものを含むいい字面だと加納さんも思っている。上方漫才の系譜をたどれば、江州音頭の玉子家円辰で、これは何人かとしゃべりながら相方をとっかえひっかえしていた。その後、砂川捨丸は紋付袴を着用し猥雑な雰囲気をなくした。そして、エンタツ・アチャコ。当初は二人漫談と名乗っていた。この時に第一次漫才ブームが起こり、「よう言わんわ」が東京でブームとなる。ラジオで初の寄席中継も行われた。第二次漫才ブームは新興演芸がミスワカナ・玉松一郎を吉本より引き抜いた昭和十三年ごろ。秋田實もこの時新興演芸に移っている。雁玉・十郎、光晴・夢若、五九童・蝶子らが活躍し、最も漫才作家が活躍した時期である。第三次漫才ブームは昭和二二年ごろ、戎橋松竹の開場に始まる。昭和二四年にはNHKラジオで全国放送の「上方演芸会」が始まり、黄金期を築いた。これは昭和四五年ごろまで続く。この時期に活躍した漫才作家が、織田正吉、足立克己、中田明成らである。しかし、一九八十年代の第四次「マンザイブーム」で漫才はしゃべくりの芸も不要となる本当の「無芸」になってしまった。「花王名人劇場」プロデューサーの澤田隆治は「作家はいらん」と言った。漫才師のキャラクターが売れる時代になったのである。
台本で売れた漫才はない。漫才台本の役割は、いわばリリーフ的なもので、漫才師のネタの補充、客からの視点を芸人に与えることなどであり、決して漫才師より目立ってはいけないのだと、加納さんは言う。
漫才はもともと「真似し漫才米もらい」と言われたように、「真似し」をエッセンスとする。「大阪人が二人寄れば漫才になる」「大阪人の好きな無駄話」と定義づけたのは秋田實。鶴見俊輔は「恥をかこうとする文化」とし、前田勇は「二人の人物がお互いに賢愚関係にあることを、何らかの手段方法で具現する芸能」とした。吉田留三郎は「漫才は芸能のカスやで。カスやから面白い」と言っている。
漫才作家にはネタを書くタイプと芸を書くタイプがいて、加納さんは後者だという。前者は量産ができる。現在の台本はネタの提供ばかりになってきたのでは、と加納さんは残念がった。また、台本作家は減少している。かつては「三組つかんだら食べていける」と言われたものだが。現在では「本読み」の習慣もないのではないだろうか。まさに芸人へのネタの提供ばかりになっているという状況があるのだ。
漫才台本の著作権が最近は認められてはいるが、ネタのタイトルに「作・加納健男」などと表記されるのは醜いとも感じて好きにはなれない。しかし、著作権料はやはりほしいし、大切にもしたい、と複雑な心境を吐露された。ダウンタウンの登場で漫才は先祖がえりしたかと思われたが、彼らが漫才をしなくなり、昔の形の漫才が消えていくという、危機感が伝わってくる内容の話であった。